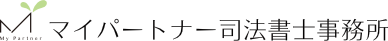司法書士として公正証書遺言を使っての遺言執行は多数経験ありますが、法務局保管遺言を使っての遺言執行は今まで経験したことがありませんでした。
法務局保管遺言は令和2年7月から始まった新しい制度であるため遺言を残した人が亡くなるという場面が発生することがまだ少ないためです。
今回は私が初めて法務局保管遺言を使って遺言執行を行ったため疑問点及び実務遂行のポイントを整理しておきたいと思います。
法務局保管遺言は自筆証書遺言との大きな違いとして家庭裁判所の検認が不要という点が挙げられます。
これは大きなメリットですし作成時に法務局へ行ける元気のある人であれば公証役場より気軽に(?)敷居が低く(?)作成できます。
しかしながら遺言執行をしてみて思いました。執行のスピード感は公正証書遺言一択であると。
逝去後の大きな流れとしては以下です。
1.戸籍収集
2.遺言書保管事実証明書の交付の請求
(遺言書保管番号がわかっていれば省略可)
3.遺言書情報証明書の交付の請求
4.遺言執行
一番大変だったことは戸籍収集に時間がかかることです。
公正証書遺言であれば亡くなった方の最後の戸籍や受遺者の戸籍で基本的には手続きが進んでいきます。早いと1週間位で遺言執行に着手できます。
しかしながら法務局保管遺言では上記3の手続きの際に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍、法定相続人全員の戸籍及び住民票が必要になってきます。
遺産を受け取らない法定相続人の分も必要です。
きょうだいが法定相続人の場合、親たちの戸籍の遡りも必要となりかなりの数の戸籍の取り寄せをするため時間がかかります。
そのため戸籍の収集、遺言書情報証明書の交付請求、と進めると1ヶ月以上はかかります。
この間を受遺者や法定相続人に待ってもらうことが必要です。
なぜ法定相続人全員の住民票が必要かというと、遺言書情報証明書が発行されると法務局は、その方以外の全ての相続人等に対して、関係する遺言書を保管している旨を通知します。
これはこれでいいのやら悪いのやらでして遺産を受け取らない人にも法務局から「被相続人〇〇さんの遺言書があります」という内容のが通知が届くこととなります。(とはいえ遺言執行者は就任後法定相続人へ通知をしないといけないので法務局からお知らせが来ても特に大勢に影響はないのかもしれません。)
今回は皆さんの理解が得られていた事案でしたので問題はなかったのですが相続人間で争いがあるようなケースは早く不動産の名義変更をしないと後々大変なことになることもあるので法務局保管遺言は向いていないと思いました。
金融機関の相続手続きや登記手続き的には特に遺言書情報証明書で困ったことはなかったです。
やはり公正証書が便利だと実感しましたので今後遺言書を作成する方には公正証書を勧めたいと思います。